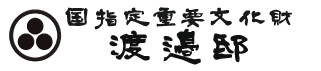渡邉邸の土蔵 -歴史を紡ぐ6棟の倉庫
渡邉邸の母屋と6つの土蔵は、1954年(昭和29年)から1978年(昭和53年)にかけて国の重要文化財に指定されました。現存する6棟の土蔵は、天明期から明治期にかけて建造され、約100年にわたる土蔵建築の変遷を今に伝えています。
かつての豪農屋敷には12棟の土蔵があったことが慶応3年の屋敷図から確認されており、現存する6棟は当時の繁栄を物語る貴重な文化遺産となっています。

土蔵の配置と設計の特徴
渡邉邸の土蔵は一見雑然と配置されているように見えますが、実は深い配慮が感じられる設計が施されています。この地方の豪農の家では、土蔵を一列に整然と並べるのが一般的でした。しかし、渡邉家では敷地内の一地点から5つの土蔵を一望できるような配置が取られ、実用性と景観を両立させています。
さらに、各土蔵はその役割に応じた設計がされており、収納する物の特性に合わせた環境が整えられています。特に金蔵は防犯性を高めるため、内壁全体が鉄格子で覆われており、その堅牢さから当時の貴重品管理の重要性がうかがえます。
さらに、各土蔵はその役割に応じた設計がされており、収納する物の特性に合わせた環境が整えられています。特に金蔵は防犯性を高めるため、内壁全体が鉄格子で覆われており、その堅牢さから当時の貴重品管理の重要性がうかがえます。
現存する六棟の土蔵
米蔵 | 建造:天明3年(1783年) |
|---|---|
味噌蔵 | 建造:天明7年(1787年) |
金蔵 | 建造:19世紀中頃 |
寶蔵 | 建造:明治初期 |
新土蔵 | 建造:19世紀中頃 |
裏土蔵 | 建造:明治30年(1897年) |
渡邉邸の建築美を詳しく見る