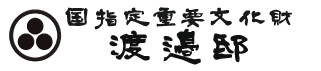母屋 格式と機能が調和する建築様式
渡邉邸は、関川村下関の代表的建築様式である「撞木造り」を採用しており、街道に面し並行に建つ前棟と、それに直角に建つ後棟の2つの棟からなるT字型の屋根構造が最大の特徴です。母屋は桁行35.1メートル、梁間17.8メートルという壮大な規模を誇り、その存在感は見る者を圧倒します。

空間構成に見る生活の知恵
建物内部は、実用性と格式の見事な調和を示しています。南北に貫通する土間は、採光のための吹き抜けを設けることで、自然光を最大限に活用する工夫が施されています。この空間を支える柱や梁には、厳選されたけやきなどの巨木が使用されており、建物の強度を高め、構造美を際立たせています。
特筆すべきは、約40室という広大な空間構成です。茶の間、中茶の間、台所と連なる空間には段差が設けられ、身分制が敷かれていました。75名もの使用人と家族が暮らした共同体の営みを今に伝えています。一方、大座敷は書院造りとなっており、武者隠しまであります。しかし柱や天井の竿縁は面皮付きになっており、数奇屋風の意匠が施されています。客人をもてなす空間は建てられた時から、そのままの姿で権威と美意識を今に伝えています。
特筆すべきは、約40室という広大な空間構成です。茶の間、中茶の間、台所と連なる空間には段差が設けられ、身分制が敷かれていました。75名もの使用人と家族が暮らした共同体の営みを今に伝えています。一方、大座敷は書院造りとなっており、武者隠しまであります。しかし柱や天井の竿縁は面皮付きになっており、数奇屋風の意匠が施されています。客人をもてなす空間は建てられた時から、そのままの姿で権威と美意識を今に伝えています。
江戸時代の建築美術 渡邉邸母屋の設え
建築年 | 文化14年(1817年)再建 |
|---|---|
建築様式 | 撞木造り(しゅもくづくり) |
規模 | 母屋 桁行:35.1メートル |
部屋構成 | 総部屋数:約40室 |
土間構造 | ・南北に貫通する大空間 |
座敷意匠 | ・大座敷:数奇屋風の繊細な意匠 |
特殊工法 | ・庇:はね木による支持構造 |
使用材料 | ・柱材:けやきの巨木良材 |
渡邉邸の建築美を詳しく見る