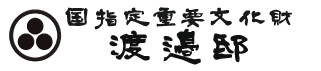渡邉邸の歴史|越後の豪農400年の軌跡

渡邉家の歴史概要
越後国(現在の新潟県)を代表する豪農として知られる渡邉家は、寛文7年(1667年)、初代当主・儀右衛門善高が村上藩主松平大和守直矩の郡奉行から隠居し、現在地に転居したことに始まります。以来、米沢藩との深い関わりを持ちながら、地域経済の発展に大きく貢献してきました。
主な歴史
創業期:江戸時代前期
寛文7年(1667年)
初代当主儀右衛門善高が現在地に転居
寛文9年(1669年)
二代当主三左エ門善延が下関村に土着
延宝4年(1676年)
酒造業を開始
発展期:江戸時代中期
享保16年(1731年)
持高177石を記録
明和2年(1765年)
米沢藩への貸金が累計2万7000両に達する
明和6年(1769年)
米沢藩より加禄60石を受け、計250石となる
隆盛期:江戸時代後期
文化14年(1817年)
現在の母屋が改築される
文政11年(1828年)
幕府より苗字帯刀を許される
近代以降
昭和29年(1954年)
母屋・米蔵・味噌蔵・金蔵が国の重要文化財に指定
昭和38年(1963年)
庭園が国の名勝に指定
昭和53年(1978年)
宝蔵・新土蔵・裏土蔵なども重要文化財に追加指定
平成21年~26年(2009年~2014年)
「平成の大修理」で母屋・外塀・土蔵を修復
渡邉家の事業と社会貢献
主な事業活動
- 酒造業(延宝4年開始)
- 廻船業
- 金融業(各藩への貸付)
- 農業経営(小作地の管理)
社会への貢献
- 米沢藩への財政支援
- 地域の発展への尽力
- 文化財としての建造物の保存
時代背景
渡邉家が興隆した江戸時代中期から後期は、上杉家の米沢藩が財政再建に取り組んでいた時期と重なります。特に上杉鷹山の藩政改革期には、渡邉家は重要な財政支援者として大きな役割を果たしました。
渡邉家の歴史年表
創業期:江戸時代前期(1667年~)
上杉家の会津から米沢への国替え後、越後国は様々な変化を経験した時期でした。
寛文7年(1667年)
初代当主儀右衛門善高が村上藩主松平大和守直矩の郡奉行から隠居、現在地に転居
当時の村上藩は17万5000石の外様大名が治める藩でした。
延宝4年(1676年)
酒造業を開始。後の経済基盤となる
発展期:江戸時代中期(1731年~)
米沢藩との関係が深まり、金融業を通じて大きく発展した時期です。
享保16年(1731年)
持高177石を記録。地域有数の豪農として確立
明和2年(1765年)
米沢藩への貸金が累計2万7000両に到達
上杉鷹山との関係
天明6年(1786年)には上杉鷹山より手遊びの弾弓を下賜されるなど、単なる金融関係を超えた信頼関係を築いていました。
隆盛期:江戸時代後期(1800年~)
経済力を背景に、建築物の充実や文化的活動も行われた時期です。
享和2年(1802年)
家族6人、譜代2人、召使40人、馬8頭、手作り田50町歩の大所帯を記録
文化14年(1817年)
現存する母屋を改築。村上藩大工棟梁の伊兵衛が担当
この改築は、前年の火災からの復興として行われました。
渡邉家の経営と文化
多角的な経営基盤
- 酒造業:延宝4年(1676年)開始、天保7年(1836年)には3株を所有
- 金融業:米沢藩を中心に、鶴岡藩、黒川藩、長岡藩などへの貸付
- 農業経営:文政11年(1828年)時点で33村に小作地を所有
文化的側面
- 六代当主善富は俳諧を好み、松下堂、李郷の号で知られる
- 上杉鷹山との交流により、数々の書や美術品を拝領
- 庭園は江戸時代中期の作庭で、1963年に国の名勝に指定
歴史的価値と文化財指定
昭和29年(1954年)
母屋・米蔵・味噌蔵・金蔵が重要文化財に指定
昭和53年(1978年)
宝蔵・新土蔵・裏土蔵・堀・棟札・屋敷図・宅地が追加指定
概略年表
| 年 号 | 西 暦 | 事 項 |
| 慶長 3年 | 1598 | 上杉景勝越後国より会津へ移封120万石。下関村、村上藩領となる |
| 慶長 6年 | 1601 | 上杉景勝会津より米沢30万石へ移封 |
| 寛文 4年 | 1664 | 米沢藩15万石になる |
| 寛文 7年 | 1667 | 初代当主儀右衛門善高は村上藩主松平大和守直矩の家臣で郡奉行として活躍していたが、大和守が姫路へ国替えのとき、家督を嗣子に譲って桂村に隠居、現在地に転居 |
| 寛文 9年 | 1669 | 二代当主三左エ門善延桂村より下関村に土着 |
| 延宝 4年 | 1676 | 酒造業を始める |
| 宝永 4年 | 1709 | 幕府領(~正徳2年) |
| 正徳 2年 | 1712 | 館林藩領(~享保13年) |
| 享保 5年 | 1720 | 米沢藩へ貸金の初見 「家内渡掟書帳」をつくる |
| 享保 9年 | 1724 | 三代当主善久相続 |
| 享保 14年 | 1729 | 幕府領(鶴岡藩預り~寛延2年) |
| 享保 16年 | 1731 | 持高177石 |
| 享保 17年 | 1732 | 四代当主善永相続。この人庭園を造る |
| 享保 18年 | 1733 | 大蔵神社再建 |
| 寛延 3年 | 1750 | 幕府領(長岡藩預り~宝暦2年) |
| 宝暦 3年 | 1753 | 幕府領(米沢藩預り~寛政1年) |
| 明和 2年 | 1765 | 米沢藩へ貸金累計2万7000両、返金累計1万9000両ほかに鶴岡・黒川・長岡藩へも貸金 五代当主英良相続 |
| 明和 6年 | 1769 | 米沢藩の江戸城西丸普請手伝いに3000両を用立て、加禄60石、計250石 上関分家義右衛門禄140石 |
| 明和頃 | 三日市藩へ貸金1350両 | |
| 安永 1年 | 1772 | 六代当主善富相続。渡邉家俳諧の祖となる。号は松下堂、李郷 |
| 安永 2年 | 1773 | 禄250石、勘定頭格 |
| 天明2~5年 | 1782 | 天明の飢餓 |
| 天明 5年 | 1785 | 四~六代の貸金元金6万1742両、返済金7万595両、差引8853両。ほかに1200両差し上げ 七代当主善映、中条分家より養子相続。上杉鷹山隠居 |
| 天明 6年 | 1786 | 禄450石。上杉鷹山より手遊びの弾弓下賜。古借1万1360両を無利子、永年賦償還を承諾。上関分家儀右衞門禄200石 |
| 寛政 1年 | 1789 | 幕府領(高田藩預り~寛政4年) |
| 寛政 10年 | 1799 | 「家の掟」を定める |
| 享和 1年 | 1801 | 小作米1497俵。蔵を下関、高田、赤谷、保内、神納に置く |
| 享和 2年 | 1802 | 家族6人、譜代2人召使40人、馬8頭、手作り田50町歩 上杉鷹山の書幅を賜る |
| 文化 2年 | 1805 | 囲い蔵をつくり飢餓に備う |
| 文化 10年 | 1813 | 嘉蔵より長政・伊勢国新田60町歩を617両で入手 |
| 文化 13年 | 1816 | 失火、翌14年改築(大工棟梁は村上藩伊兵衛) |
| 文化 14年 | 1817 | 母屋が改築され、現在の邸宅となる |
| 文政 4年 | 1821 | 城塚新田54町歩余を新発田町住吉屋より2330両で購入 |
| 文政 5年 | 1822 | 上杉鷹山没 |
| 文政 11年 | 1828 | 幕府より用金上納につき苗字帯刀を許される。小作地33村 |
| 天保 3年 | 1832 | 八代当主善保相続 |
| 天保 7年 | 1836 | 酒造株3株 |
| 天保 14年 | 1843 | 「大検大意」を定める |
| 弘化3~4年 | 1846 | 米沢藩へ雲伯両国の鉄2万6000貫を周施 |
| 嘉永 5年 | 1852 | 長岡藩へ2300両を用立てる |
| 嘉永6~7年 | 1853 | 品川台場築造費として1550両を幕府に上納 |
| 安政 2年 | 1855 | 九代当主善一相続 |
| 安政 3年 | 1856 | 幕府への献金慶応まで相次ぐ(1200両)。家財傾く |
| 慶応 4年 | 1868 | 戊辰戦争に米沢藩のために奔走(米沢藩預り) |
| 明治 12年 | 1879 | 十代当主善郷相続。村の素封家として政界財界で活躍 |
| 明治 27年 | 1894 | 地価11万6000円、1476町歩余、うち山林1080町歩余 |
| 大正 7年 | 1918 | 米坂線誘致に尽力 |
| 昭和 8年 | 1933 | 十一代当主萬寿太郎相続。村の素封家として政界財界で活躍 |
| 昭和 11年 | 1936 | 米坂線全通 |
| 昭和 20年 | 1945 | 関谷村長、29年関川村長 |
| 昭和 27年 | 1952 | 新潟県人文研究会より「本渡邉家資料抄」発行される |
| 昭和 29年 | 1954 | 母屋・米蔵・味噌蔵・金蔵、国の重要文化財に指定 |
| 昭和 35年 | 1960 | 県人事委員会委員長 |
| 昭和 38年 | 1963 | 庭園、国の名勝に指定 |
| 昭和 39年 | 1964 | 6月16日新潟地震 M7.5 新潟地震の災害復旧工事として |
| 昭和 40年 | 1965 | 新潟地震災害復旧工事として、味噌蔵・米蔵を修理 |
| 昭和 42年 | 1967 | 3月13日 「重要文化財渡辺家保存会」発足・8月28日羽越水害 |
| 昭和43年~ 昭和59年 | 1968~ 1984 | 羽越水害の復旧から始まり「昭和の大修理」を行なう |
| 昭和 53年 | 1978 | 宝蔵・新土蔵・裏土蔵・堀・棟札・古図・宅地9.193m、国の重要文化財に指定 |
| 昭和 59年 | 1984 | 十二代当主和彦養子相続 |
| 昭和 62年 | 1987 | 土蔵より日本最古の日本酒見つかる (財)日本ナショナルトラスト観光資源調査「越後下関の町並み」 |
| 平成 4年 | 1992 | 関川村発行の「北越の豪農 渡辺家の歴史」が発行される |
| 平成 7年 | 1995 | 2月~7月までNHKドラマ「蔵」のロケ地となり全国的に知られる |
| 平成 20年 | 2009 | 十三代当主孝弘養子相続 |
| 平成21年~ 平成26年 | 2009~ 2014 | 総工費8億円をかけた「平成の大修理」で母屋・外塀・土蔵を修復 |